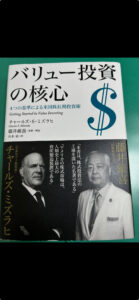【税理士がやさしく解説】 相続税の基礎と生前贈与のコツ知らないと損する相続対策
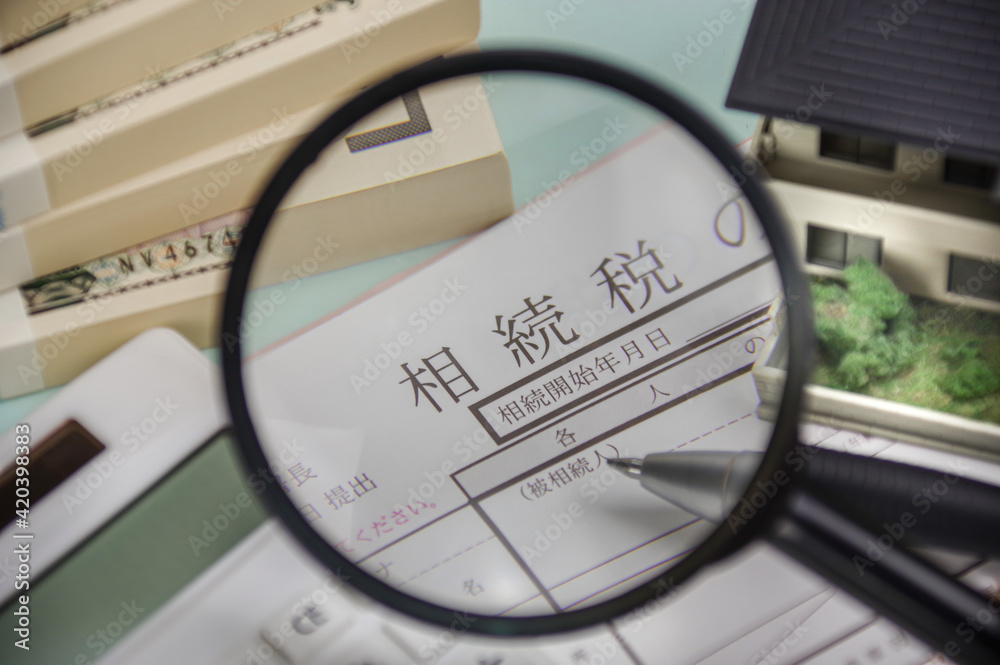
「相続税」と聞くと、どこか難しそうで、自分には関係ないと思っている方も多いかもしれません。
しかし、実際には「家や土地を持っている」「生命保険に入っている」「預貯金がある」といったご家庭でも、条件によっては相続税がかかる場合があります。
相続税の仕組みを正しく理解しておくことは、将来のトラブルを防ぎ、家族が安心して暮らすための第一歩です。
この記事では、税理士の立場から相続税の基本と、生前贈与を活用した賢い相続対策をやさしく解説します。
相続税とは?基本の仕組みをわかりやすく解説
相続税とは、亡くなった方(被相続人)の財産を相続や遺言によって受け取った人に課される税金です。
国がこの税金を設けている目的は「富の再分配」と「公平な課税」
つまり、財産が一部の家庭に集中しすぎないようにするための仕組みでもあります。
課税の対象となる財産は、現金・預貯金・不動産・株式などの有価証券のほか、貴金属や自動車、骨董品、ゴルフ会員権など多岐にわたります。
また、死亡保険金や退職金の一部も「みなし相続財産」として扱われる場合があります。
一方で、墓地や仏壇、仏具などの祭祀財産は原則非課税です(ただし、高額な金製品などは例外となる場合もあります)。
相続税がかかるかどうかの判断基準「基礎控除」
相続税は、亡くなった方のすべての財産から借入金や葬儀費用などを差し引いた「正味の遺産額」が、基礎控除額を超えた場合にかかります。
基礎控除額は次の計算式で求められます。
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
たとえば法定相続人が3人の場合、3,000万円+600万円×3=4,800万円。
この金額を超えた分に相続税がかかります。
財産が5,000万円あれば、超過額200万円に対して課税されるというわけです。
ただし、相続税の税率は10%~55%までの累進課税で、金額が大きくなるほど税負担が増える仕組みになっています。
生命保険の非課税枠を上手に活用
相続税対策としてよく使われるのが、生命保険の「非課税枠」です。
受け取る保険金には、「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠があり、たとえば相続人が3人いれば1,500万円まで非課税になります。
この枠を上手に活用すれば、相続税の負担を抑えつつ、相続発生後の生活資金を確保できます。
また、生命保険金は受取人がすぐに現金を受け取れるため、納税資金の確保にも役立ちます。
「財産は土地が中心で現金が少ない」という方にとって、保険はとても有効な相続対策です。
配偶者の税額軽減は大きなポイント
相続税には、配偶者が相続する場合に使える「配偶者の税額軽減」という特例があります。
配偶者が相続する財産が1億6,000万円以下または法定相続分以下であれば、相続税はかかりません。
この制度を活用すれば一次相続(最初の相続)の税負担は大幅に軽減できます。
ただし、配偶者に財産を集中させすぎると、次の相続(二次相続)で子どもにかかる税金が増える可能性があります。
「一次相続で減税」「二次相続でバランスよく分配」——この2段構えの計画が、相続対策ではとても重要です。
生前贈与でできる相続税の節税
相続税の節税で欠かせないのが「生前贈与」です。
生前贈与とは、生きているうちに家族などへ財産を贈ること。
毎年110万円までなら「暦年贈与」として贈与税がかかりません。
この非課税枠を活用して、複数年にわたり少しずつ財産を贈与することで、将来の相続財産を減らすことができます。
贈与を有効にするには、贈与契約書を作成すること、そして受け取った人が実際に財産を管理・使用していることが重要です。
「名義だけの贈与」と見なされると、相続税の対象に戻されることがあるため注意が必要です。
また、「相続時精算課税」「教育資金の一括贈与(最大1,500万円まで非課税)」「結婚・子育て資金の一括贈与(最大1,000万円まで非課税)」「住宅取得資金の贈与」などの特例もあります。
どの制度を使うかによって効果が大きく異なりますので、実行する前に税理士へ相談することをおすすめします。
税理士に相談するメリット
相続税の申告や対策は、財産評価や特例の適用など専門的な判断が求められます。
税理士は、土地・建物・株式などの評価を正確に行い、控除や特例を最大限に活用することで、税法の範囲内で税負担を軽減します。
さらに、申告書の作成から税務署への提出、税務調査対応まで一貫して任せられるため、遺族の心理的・時間的負担を大幅に減らすことができます。
「相続税のことを考えるのはまだ早い」と思う方も多いですが、早めの対策こそが最大の節税になります。
相続は多くの方にとって一生に一度の出来事。
知らないまま放置するより、今から少しずつ準備をしておくことで、家族の将来を安心して迎えることができます。
相続や贈与に関する不安がある方は、ぜひ一度、相続に強い税理士へご相談ください。
それが「知らないと損する相続」から家族を守る最良の方法です。