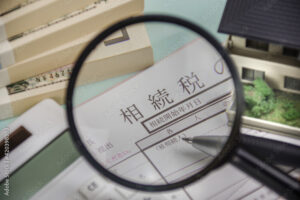あなたの「想い」をカタチに:税理士が教える、もめないための「遺言」のススメ

「遺言」と聞くと、「まだ早い」「大げさだ」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、これはあなたが大切に築き上げてきた財産を、あなたの心からの願い通りに、そして残された家族が円満に受け継ぐための、最も確実な「愛のメッセージ」です。
税理士として多くの相続案件に関わる中で、遺言書がないために、ご家族が、故人の意思とは違う形で相続をせざるを得なくなったり、遺産分割で感情的な争いを抱えてしまう悲しい現実を何度も見てきました。
このブログでは、一般の方向けに、「遺言」の基本、種類、そして最も重要な「もめないためのポイント」を分かりやすくお伝えします。
第1章:なぜ「遺言」が必要なのか?
遺言書がない場合、財産の分け方は、原則として法律で定められた「法定相続分」に基づいて、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で決めることになります。
この「話し合い」こそが、多くの場合で争いの種となります。
- 「想い」が伝わらないリスク: 「長男には家業を継いでもらうから多めに」「献身的に介護してくれた次女には感謝の気持ちを込めて」といった故人の真の願いは、書面で残されていなければ、ただの「希望」として扱われ、実現しない可能性があります。
- 相続手続きが停滞するリスク: 遺産分割協議がまとまらないと、銀行預金の解約や不動産の名義変更など、すべての相続手続きがストップしてしまいます。
- 特定の財産を渡せないリスク: 内縁の配偶者や、お孫さんなど、法定相続人ではない人に財産を渡したい場合、遺言書がなければ法的にその願いを実現することはできません。
遺言書は、これらのリスクを未然に防ぎ、「あなたの最期の意思を法的に実現する」唯一の手段なのです。
第2章:遺言書の主な3つの種類
遺言書には、法律で定められた方式があり、主なものは以下の3つです。
| 種類 | 作成者 | 費用 | 安全性・確実性 | 検認手続き*¹ |
| 自筆証書遺言 | 遺言者本人 | ほぼゼロ | 低〜中 | 原則必要(法務局保管制度を利用すれば不要) |
| 公正証書遺言 | 公証人(公証役場) | 費用がかかる | 非常に高い | 不要 |
| 秘密証書遺言 | 遺言者本人 | 費用がかかる | 低 | 必要 |
*¹ 検認:家庭裁判所が相続人に対し遺言の存在と状態を知らせる手続き。公正証書遺言は不要。
一般的に利用されるのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つです。
1. 自筆証書遺言(最も手軽)
- メリット: 費用がほとんどかからず、思い立ったらすぐに作成でき、内容を秘密にできます。
- デメリット: 形式(全文自筆、日付、署名捺印など)の不備で無効になるリスクが非常に高いです。また、紛失・隠蔽・改ざんのリスクもあります。
- 【重要】法務局保管制度: 令和2年7月から、自筆証書遺言を法務局で保管できる制度が始まりました。これにより、形式不備の確認と、紛失・隠蔽のリスク回避、さらに検認手続きが不要になるという大きなメリットが加わりました。
2. 公正証書遺言(最も確実)
- メリット: 公証人という法律の専門家が作成するため、形式不備で無効になるリスクがほぼなく、最も確実です。原本は公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配もありません。検認手続きも不要で、相続開始後すぐに手続きを進められます。
- デメリット: 費用がかかり、作成時に証人2名と公証人が立ち会うため、内容を完全に秘密にすることはできません。
【税理士の視点】 相続が発生した後、ご家族がスムーズに手続きを進めるためには、公正証書遺言が最もおすすめです。特に、財産が多い方や、特定の相続人に多くの財産を渡したいなど、内容が複雑な場合は、迷わず公正証書遺言を選びましょう。
第3章:遺言書で「できること」と「注意点」
遺言書に書けば、何でも法的な効力を持つわけではありません。法律上の効力が認められる主な事項は以下の通りです。
遺言で効力を持つ主な事項(法的に実現可能)
- 財産の処分に関すること:
- 誰に、どの財産をどれだけ渡すか(遺贈、相続分の指定)
- 特定の財産の分割方法を指定
- 身分に関すること:
- 認知(婚外子を自分の子として認めること)
- 推定相続人の廃除(虐待などを行った相続人から相続権を奪う)
- 相続手続きに関すること:
- 遺言執行者の指定(最も重要!)
【最重要】「遺言執行者」の指定
遺言執行者とは、遺言書に書かれた内容を実現するための手続き(預金の解約、不動産の名義変更など)を行う人です。
遺言執行者が指定されていれば、相続人全員のハンコ(実印)を集めなくても、執行者一人の権限で手続きを進めることができます。
もし遺言執行者を指定しないと、相続人全員が協力して手続きを進めなければならず、結果的に手続きが滞ってしまう可能性があります。信頼できる親族や、専門家(弁護士、司法書士、税理士など)を指定しましょう。
遺言でもできないこと(注意点)
- 付言事項(お願い事): 感謝の言葉や家族へのお願いなど、法的な効力はありませんが、家族間の争いを防ぐための重要なメッセージとなります。ぜひ書いてください。
- 遺留分(いりゅうぶん): 兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限相続できる権利(遺留分)が法律で保障されています。遺言で特定の相続人に全財産を渡すと書かれていても、他の相続人は遺留分を請求することができます。この点も考慮して、財産の配分を検討する必要があります。
第4章:「争族」を防ぐための税理士からのアドバイス
遺言書を作成する上で、税理士の視点から特に重要だと考えるポイントを挙げます。
- 財産目録は正確に作成する
- 全ての財産(不動産、預貯金、株式、保険、借金など)を明確にし、どの財産を誰に渡すのか具体的に指定しましょう。「財産の半分」ではなく、「〇〇銀行の口座全額」「〇〇市〇丁目所在の土地」のように特定することが大切です。
- 相続税のことも考えて配分する
- 特定の財産を特定の相続人に集中させると、相続税の負担が偏ったり、適用できたはずの特例(小規模宅地等の特例など)が使えなくなったりする場合があります。財産の配分は、税金のことも考慮して専門家と相談しながら決めましょう。
- 付言事項で「想い」を伝える
- 遺言書は、財産を分けるための書類であると同時に、あなたの「最期のラブレター」です。なぜその財産配分にしたのか、家族への感謝の気持ち、残りの人生を楽しんでほしいという願いなどを付言事項として記すことで、残されたご家族の気持ちを和らげ、「争族」を防ぐ大きな力となります。
まとめ
遺言書の作成は、決して「死の準備」ではなく、「大切な家族への配慮」であり、「残りの人生を自分らしく生きるための安心の備え」です。
今日まで懸命に築き上げてきたあなたの財産と、あなたの想いを、確実に未来へ繋ぐために、ぜひ元気なうちに遺言書の作成をご検討ください。
ご不明な点や、専門家のサポートが必要な場合は、お気軽にご相談ください。あなたの「想い」の実現を全力でサポートいたします。